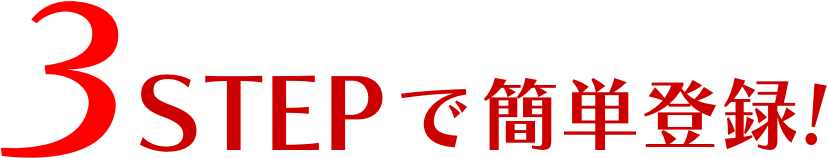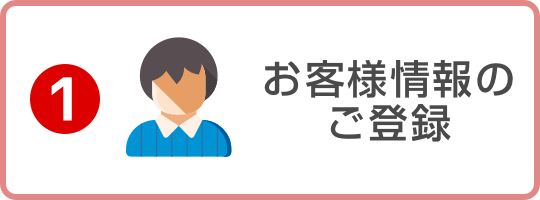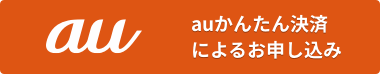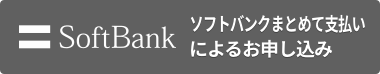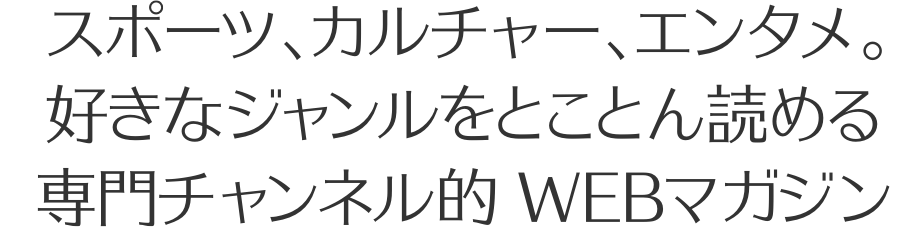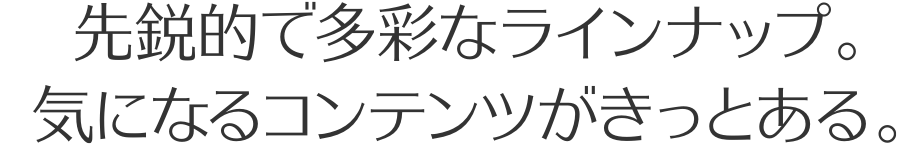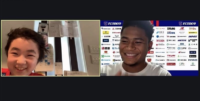「58クラブがそれぞれの地域で輝く」ことと「トップ層がナショナル(グローバル)コンテンツとして輝く」ことを同時に検討。Jリーグが掲げようとする新たな成長戦略とは【Jリーグ社員総会後記者会見/無料公開】

会見中の野々村芳和Jリーグチェアマン。
11月15日にJリーグは社員総会を開催した。午後にはオンライン形式で社員総会後記者会見が開催され、登壇した野々村芳和チェアマンは、Jリーグ開設から30年を機に、今後の「30年、40年、50年に向けて変えていかなくてはいけないところがありました」と前置きし、新たな成長戦略とそれを実現するための構造改革が必要だろうと述べた。
◆配分金の制度が結果を重視したものになる?
Jリーグ加盟クラブも開設時の10クラブから58クラブに増え、奈良クラブに加えてFC大阪のJ3加盟が実現すれば来季は60クラブになろうかという現在、意思決定のガバナンスにもメスを入れなければならないと、Jリーグという組織の構造改革についても一定の時間を割いて説明がなされたが、ここでは成長戦略に絞ってお伝えしていく。
Jリーグが検討した「成長テーマその1」は『58クラブがそれぞれの地域で輝く』。その手段は「ローカル露出拡大」であり、福島、富山、愛媛、熊本、鹿児島で10月から『KICK OFF!+地名』がタイトルとなっているクラブ単位ではなく各地域のサッカーを盛り上げる応援番組を開始(YouTubeのJリーグ公式チャンネルでも配信)したところ、半年前の4月と比較してこの5つの地域に於けるサッカー関連情報の露出量が大幅に拡大した。具体的には福島の福島中央テレビが237パーセント増(3分11秒→7分33秒)、富山のチューリップテレビが2,830パーセント増(50秒→23分35秒)、愛媛の南海放送が163パーセント増(3分8秒→5分6秒)、熊本のテレビ熊本が749パーセント増(17分29秒→2時間10分55秒。後者の時間は1試合の試合中継1時間50分を含む)、鹿児島の鹿児島放送が1,024パーセント増(6分23秒→34分39秒)の伸びを示したという。
また、注力試合に指定した公式戦ではJリーグのスタッフも運営に加わったという。リーグ策として各クラブのそれぞれの地域に於ける価値、存在感を高めようとする意識があるようだ。
他方、Jリーグの放映権料を上げるためにはJリーグそのものの価値を高めなければならず、リーグ全体を牽引するトップ層のクラブを生み出すべく、より競争の意識を強めるために配分金の仕組みを変えることを検討中であるという旨を野々村チェアマンは語っていた。これが「成長テーマその2」の『トップ層がナショナル(グローバル)コンテンツとして輝く』であり、資料では競技水準を向上する「フットボール改革」を掲げている。sの改革を成し遂げるべくカテゴリーの差や人気の高低によって配分金の割合を変えていこうとする考えがあるようで、これによってJリーグはいよいよ護送船団方式の色を薄め、競争の論理をより強調することでリーグ全体の質を高める方向に舵を切ることになる。
「成績やファンがどのくらい増えたかという結果配分を中心にしたものにシフトしながら競争していく。ヨーロッパの大きなリーグと比べて日本の中で圧倒的なチームはどこかというと、この10年でも2~3チームが複数回優勝しているだけで、まだまだそこは競争のフェイズにあると思うんですね。いま、場合によっては下のカテゴリー、J2にいたとしても十分日本をリードしていくようなビッグクラブになる可能性があるというのがいまのJリーグだと思いますから、そこで引っ張っていってもらうようなクラブに出てきてもらいたいという想いはあります」(野々村チェアマン)
JFLへの降格が始まるかもしれない2023シーズンは、日本のトップを決める競争へのキックオフともなりそうだ。
◆野々村芳和チェアマンに訊く
FC東京の応援番組枠がなくなったこのタイミングということもあり、野々村チェアマンにどう思うかを訊ねてみた。以下は後藤勝による質疑のほぼ全文起こし。
質問(以下、後藤):(※各クラブの応援番組ではなく地域ごとにサッカーを盛り上げる応援番組を放送して露出を増やしていくというそこまでの話の流れを受けて)地域のサッカーそのものの応援番組で露出を増やしていくという話だったが、FC東京では先日MXテレビに於けるクラブの応援番組枠そのものがなくなってしまった。喜ばしくないことと考えているのか、どうなのか。
野々村芳和チェアマン(以下、チェアマン):個別の話をするとニュアンス的にもなかなか難しいと思うので、いまの質問に直接は答えないですけど、でもふだんからサッカーと触れる機会を設けていくかというのは、日本のメディア環境に於いてはまだまだ重要だと思うので、いまのFC東京の話に限らず、やっぱりどのクラブでもなるべく触れやすいようなメディアでの露出をつくっていくことはリーグとしてはやりたいと思っています。もちろんそこに投資をするということ。基本的には投資をしないと成長はないと思っていますから、いま投資しなければいけないところはそういったところなのかなとも思っています。
後藤:各クラブ、地上波ではないがInstagramやYouTubeでの情報発信を強化していることはそれはそれでよい?
チェアマン:もちろんです。どこのIT系の企業も地上波にCM出したりするくらい地上波の環境はほかの国とちがうものがあるので、デジタルな部分はJリーグも各クラブも数年かけて力をつけてきたものはあると思うんですけど、より成長のスピードを上げるという意味でも、または新たなお客さんにアプローチするという意味でも、地上波のところをひとつのきっかけにするというのは、考え方としては悪くない筋かなと思っています。
後藤:(※配分金の傾斜をJ1の割合を増やす方向で検討中という話の流れを受けて)ざっくりした質問で申し訳ないが、トップ層のフットボールの成長をどうイメージしているか。配分金の傾斜等によってよい人材が集中することで上位3、4クラブが強くなるということが起こりやすくなるイメージなのか、それとも戦術的にモダンフットボールを磨く環境がより研ぎ澄まされるようになるというイメージなのか。
チェアマン:まあ、それは両方じゃないですか。勝つことで利益を得られる、競争が強くなれば、こういう監督を連れてきて、とか、こういうアカデミーダイレクターを連れてきて育成しなきゃ、とか。もっと言うとこういう強化スタッフに投資しなくてはとか、こういう経営陣に投資しなくては、というふうにたぶんなっていくと思うんですよね。日本のサッカーは30年前にプロ(リーグ)が出来て、選手はプロになりました。そのあとよく言われたのが「指導者もプロになりました」というふうになってきた。で、ここからはフロントも含めたクラブ全体がどうプロフェッショナルになれるかというその競争をより意識してもらうためには、やっぱりピッチ上の順位とか人気とかいうところの競争がベースになって、どこに投資したらいいのかなということを考えるきっかけが必要だと思うので、短期的に戦術的にどうこうというよりは、サッカー界全体の意識をより変えていくための変化が必要だとぼくは思っています。
(後藤の質疑は以上)
———–
■ https://www.amazon.co.jp/dp/B00NNCXSRY後藤勝渾身の一撃、フットボールを主題とした近未来SFエンタテインメント小説『エンダーズ・デッドリードライヴ』(装画:シャン・ジャン、挿画:高田桂)カンゼンより発売中!
———–