この采配は後々に語り継がれる歴史の1ページとなるだろう [ACL5節全北戦レビュー] (藤井雅彦) -1,804文字-
アウェイゲームほどではなかったが、やはり全北現代のプレッシャーの迫力はすさまじかった。「ウチとは圧力が違う」(栗原勇蔵)。ボールを持ってもそれほど高い技術や戦術を要していないが、ボールを持たないときの守備意識と切り替えの早さ、そしてチーム全体に根付く規律は本当に素晴らしい。鋭い出足でマリノスから自由を奪い、どの位置でも簡単にパス交換させてくれなかった。元来ビルドアップが不得手なチームはさらに苦しい状況に追い込まれ、GK榎本哲也へのバックパスが増える。榎本や両CBからのロングボールは簡単にはね返され、相手ボールとなる。
 ここで少しだけ技術的な話をしよう。フィジカルに勝る相手はヘディングが強いだけでなく、うまかった。たとえばJリーグにおいて中澤佑二はヘディングでのクリアボールを味方に届ける可能性が高い選手だ。周囲のサポートも欠かせないとはいえ、しっかり状況判断できているからクリアではなくパスにできる。中澤にあって栗原にないものは、そういった細部の技術ではないか。そして全北現代の選手は皆一様にその技術が高かった。肉弾戦ではJリーグトップクラスであろうマリノスに対して、ヘディングを基調としたフィジカルで圧倒した。これは日本人と韓国人の差と言い換えることができるかもしれない。
ここで少しだけ技術的な話をしよう。フィジカルに勝る相手はヘディングが強いだけでなく、うまかった。たとえばJリーグにおいて中澤佑二はヘディングでのクリアボールを味方に届ける可能性が高い選手だ。周囲のサポートも欠かせないとはいえ、しっかり状況判断できているからクリアではなくパスにできる。中澤にあって栗原にないものは、そういった細部の技術ではないか。そして全北現代の選手は皆一様にその技術が高かった。肉弾戦ではJリーグトップクラスであろうマリノスに対して、ヘディングを基調としたフィジカルで圧倒した。これは日本人と韓国人の差と言い換えることができるかもしれない。
前半を振り返り、中村俊輔は「前半は勝てる気がまったくしなかった」と苦笑いする。1-0というスコア以上の差を感じたのは選手だけではないはずだ。中村は依然として調子が上がらず、齋藤学も左サイドで見せ場を作れない。競り合いでマイボールにするのが上手な伊藤翔もフィジカルに勝る相手に空中戦では歯が立たなかった。もはや攻め手がなく、万事休すかに思われた。
その状況を変えたのはハーフタイムの選手交代だった。この采配も後々に語り継がれる歴史の1ページとなるだろう。藤田祥史を投入して伊藤と2トップにシフトしたこと自体それほど驚きではないが、そのタイミングと、そして中村を定位置のトップ下から右MFに配置転換したのは勇気ある決断だった。以前も述べたが、そもそも現行の[4-2-3-1]は中村のためのシステムであり、仮に彼が不在の場合は継続するメリットはあまりない。結果的に右MFに移動した中村のボールタッチ回数は減ったが、この試合ではそれ以上にメリットが大きかった。
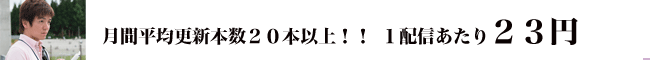
前線に起点が増えたことでボールを入れやすくなり、2トップを見ながらプレーしたことで左MFの齋藤も息を吹き返した。そもそも伊藤も藤田も2トップFWタイプで、ほとんど即興に近いながらもまずまずの距離感を保ってプレーできていた。どちらかが下がったら、片方が背後を狙う。いずれかが競り合った場面ではこぼれ球を予測したポジショニングを取る。そこに齋藤が絡む。逆転ゴールは2トップの動きを見ながらアクションを起こそうと考えていた齋藤だからこそのフィニッシュだった。
その齋藤のファインゴールについて語らないわけにはいかない。ドゥトラのスローインから無心でボレーシュートを放ち、バーをかすめながら枠をとらえた。それまでの時間帯、あるいはここ数試合のパフォーマンスは頭で考えすぎていたせいか迷いが先行していた。フィジカル面の問題よりも判断の悪さが目につき、日本代表らしからぬボールロストばかりだった。真の日本代表選手になるにはまだまだ精度を求めたいところだが、この日のように結果を変える力を有しているのは日の丸にふさわしい。偶発性の高いシュートを彼が打てたのは、ある意味で必然なのだ。
チーム全体のパフォーマンスが劇的に向上したわけではないが、勝利によってバイオリズムが一変する可能性は十分にある。ACLにおいて最終節まで望みをつなぐ価値ある勝利だったのだから、ここからの反攻を期待してもいいだろう。このタイミングで苦手な柏レイソルと対峙するのはあまりにも不運ではあるが、全北現代戦で得た勢いを有効活用して苦手チームを攻略したい。








